【宅建過去問】(平成07年問11)相続
![]()
Aには、妻B、子C・Dがあり、A及びBは、CにA所有の資産全部を相続させAの事業も承継させたいと考えているが、Cは賛成し、Dは反対している。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
- Aは、Dが反対していることを理由として、遺言で、Dを相続人から廃除することができる。
- Aが遺産の全部をCに遺贈した場合、DからCに対して遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
- Dは、Aの死亡後で遺産分割前であっても、B及びCの同意を得なければ、自己の相続分を第三者に譲渡することはできない。
- Aの死亡後、遺産分割協議をし、改めて相続人の多数決で、遺産の全部をCに承継させるしかない。
正解:2
1 誤り
推定相続人を廃除することができるのは、
- 被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、
- 推定相続人にその他の著しい非行があったとき
に限られる(民法892条)。
「被相続人の意向に反対である」というだけで廃除することはできない。
※廃除=推定相続人の持っている相続権を剥奪する制度
2 正しい
Dは、被相続人Aの子であるから遺留分を有する(民法1042条)。
したがって、Cに対して遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる(同法1046条1項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
遺留分侵害額請求(民法[33]3)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20-12-1 | 相続人の一部の遺留分を侵害する被相続人の遺言は、その限度で当然に無効である。 | × |
| 2 | 12-10-2 | Aは、「Aの財産をすべてBに遺贈する。CはBに対して遺留分侵害額の請求をしてはならない」旨の遺言をして、CをAの相続から排除することができる。 | × |
| 3 | 12-10-4 | Aは、「Aの乙建物を子Cに相続させる」旨の遺言をした場合で、子Bの遺留分を害しないとき、これをC単独の所有に帰属させることができる。 | ◯ |
| 4 | 09-10-2 | 遺留分侵害額の請求は、訴えを提起しなくても、内容証明郵便による意思表示だけでもすることができる。 | ◯ |
| 5 | 07-11-2 | [Aが死亡し、相続人はAの子であるC・Dのみ。]Aが遺産の全部をCに遺贈した場合、DからCに対して遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。 | ◯ |
| 6 | 02-11-2 | Aが遺産を子Cに遺贈していた場合、その遺贈は、配偶者B、子D及び子Eの遺留分を侵害した部分について、効力を生じない。 | × |
3 誤り
相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する(民法898条)。
そして、判例によれば、この相続財産の共有は、民法249条以下に規定する「共有」と同じ性質のものである(最判昭30.05.31)。
したがって、遺産分割前であっても、各相続人は自分の共有持分を自由に処分することができる。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
遺産分割(民法[31]5)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| (1)①共同相続の効力 | |||
| 1 | R05-01-2 | 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属し、各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。 | ◯ |
| 2 | H11-03-1 | 相続開始時に相続人が数人あるとき、遺産としての不動産は、相続人全員の共有に属する。 | ◯ |
| 3 | H07-11-3 | 共同相続人の一人は、他の共同相続人の同意を得なければ、自己の相続分を譲渡できない。 | × |
| (1)②遺産分割の対象 | |||
| 1 | R05-01-1 | 遺産である不動産から、相続開始から遺産分割までの間に生じた賃料債権は、遺産である不動産が遺産分割によって複数の相続人のうちの一人に帰属することとなった場合、当該不動産が帰属することになった相続人が相続開始時にさかのぼって取得する。 | × |
| 2 | R05-01-4 | 遺産である不動産が遺産分割によって複数の相続人のうちの一人に帰属することとなった場合、当該不動産から遺産分割後に生じた賃料債権は、遺産分割によって当該不動産が帰属した相続人が取得する。 | ◯ |
| 3 | R01-06-3 | 遺産に属する預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、共同相続人は、その持分に応じて、単独で預貯金債権に関する権利を行使することができる。 | × |
| 4 | H29-06-3 | (Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった。)遺産分割協議が成立するまでの間に遺産である不動産から賃料債権が生じていて、BとCがその相続分に応じて当該賃料債権を分割単独債権として確定的に取得している場合、遺産分割協議で当該不動産をBが取得することになっても、Cが既に取得した賃料債権につき清算する必要はない。 | ◯ |
| 5 | H15-12-3 | 相続財産である金銭債権(預金返還請求権ではない。)は、遺産分割協議が成立するまでは、相続人の共有に属し、相続人全員の同意がなければ、その債務者に弁済請求できない。 | × |
| 6 | H15-12-4 | 共同相続人の一人が相続開始時に金銭を相続財産として保管している場合、他の相続人は、遺産分割協議の成立前でも、自己の相続分に相当する金銭を支払うよう請求できる。 | × |
| (2)①指定分割 | |||
| 1 | R01-06-1 | 被相続人は、遺言によって遺産分割を禁止することはできず、共同相続人は、遺産分割協議によって遺産の全部又は一部の分割をすることができる。 | × |
| 2 | H11-03-2 | 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定めることができ、また相続開始の時から5年を超えない期間内で遺産の分割を禁ずることもできる。 | ◯ |
| 3 | H18-12-3 | 被相続人Aが、相続人BCのうちのBに特定遺産を相続させる旨の遺言をして死亡し、特定遺産以外の相続財産についての遺産分割協議の成立前にBがCの同意なく特定遺産を第三者に売却した場合、CはBD間の売買契約を無権代理行為に準じて取り消すことができる。 | × |
| (2)②協議分割 | |||
| 1 | R01-06-2 | 共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて遺産分割協議を成立させることができる。 | ◯ |
| 2 | H29-06-2 | (Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった。)Aの死亡後、いずれもAの子であるBとCとの間の遺産分割協議が成立しないうちにBが死亡したときは、Bに配偶者Dと子Eがいる場合であっても、Aの遺産分割についてはEが代襲相続人として分割協議を行う。 | × |
| 3 | H18-12-4 | B及びCの協議により甲土地をBが取得する旨の遺産分割協議を有効に成立させた場合、後にB及びCの合意があっても、甲土地をCが取得する旨の遺産分割協議を成立させることはできない。 | × |
| 4 | H07-11-4 | 遺産分割協議の結論は、相続人の多数決によって決する。 | × |
| (2)③家庭裁判所による分割 | |||
| 1 | H11-03-3 | 遺産の分割について共同相続人間に協議が調わないとき、各共同相続人は、その分割を、相続開始地の地方裁判所に請求することができる。 | × |
| (3)効果 | |||
| 1 | R05-01-3 | 遺産分割の効力は、相続開始の時にさかのぼって生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 | ◯ |
| 2 | R01-06-4 | 遺産の分割は、共同相続人の遺産分割協議が成立した時から効力を生ずるが、第三者の権利を害することはできない。 | × |
| 3 | H11-03-4 | 遺産分割の効力は、第三者の権利を害しない範囲で、相続開始の時にさかのぼって生ずる。 | ◯ |
| (4)債務の相続 | |||
| 1 | H23-10-3 | 共同相続人のうち、被相続人の唯一の資産を相続するものは、被相続人の債務のすべてを相続する。 | × |
| 2 | H19-12-3 | 相続人が単純承認した場合、被相続人の債務も、相続人が相続分に応じて承継する。 | ◯ |
4 誤り
遺産分割協議は、共同相続人全員が参加し、かつ同意しなければ成立しない(民法907条1項)。
「相続人の多数決」で結論を出すわけではない。
※全員の同意が不可能な場合は、遺産の分割を家庭裁判所に請求することになる(同2項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
遺産分割(民法[31]5)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| (1)①共同相続の効力 | |||
| 1 | R05-01-2 | 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属し、各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。 | ◯ |
| 2 | H11-03-1 | 相続開始時に相続人が数人あるとき、遺産としての不動産は、相続人全員の共有に属する。 | ◯ |
| 3 | H07-11-3 | 共同相続人の一人は、他の共同相続人の同意を得なければ、自己の相続分を譲渡できない。 | × |
| (1)②遺産分割の対象 | |||
| 1 | R05-01-1 | 遺産である不動産から、相続開始から遺産分割までの間に生じた賃料債権は、遺産である不動産が遺産分割によって複数の相続人のうちの一人に帰属することとなった場合、当該不動産が帰属することになった相続人が相続開始時にさかのぼって取得する。 | × |
| 2 | R05-01-4 | 遺産である不動産が遺産分割によって複数の相続人のうちの一人に帰属することとなった場合、当該不動産から遺産分割後に生じた賃料債権は、遺産分割によって当該不動産が帰属した相続人が取得する。 | ◯ |
| 3 | R01-06-3 | 遺産に属する預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、共同相続人は、その持分に応じて、単独で預貯金債権に関する権利を行使することができる。 | × |
| 4 | H29-06-3 | (Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった。)遺産分割協議が成立するまでの間に遺産である不動産から賃料債権が生じていて、BとCがその相続分に応じて当該賃料債権を分割単独債権として確定的に取得している場合、遺産分割協議で当該不動産をBが取得することになっても、Cが既に取得した賃料債権につき清算する必要はない。 | ◯ |
| 5 | H15-12-3 | 相続財産である金銭債権(預金返還請求権ではない。)は、遺産分割協議が成立するまでは、相続人の共有に属し、相続人全員の同意がなければ、その債務者に弁済請求できない。 | × |
| 6 | H15-12-4 | 共同相続人の一人が相続開始時に金銭を相続財産として保管している場合、他の相続人は、遺産分割協議の成立前でも、自己の相続分に相当する金銭を支払うよう請求できる。 | × |
| (2)①指定分割 | |||
| 1 | R01-06-1 | 被相続人は、遺言によって遺産分割を禁止することはできず、共同相続人は、遺産分割協議によって遺産の全部又は一部の分割をすることができる。 | × |
| 2 | H11-03-2 | 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定めることができ、また相続開始の時から5年を超えない期間内で遺産の分割を禁ずることもできる。 | ◯ |
| 3 | H18-12-3 | 被相続人Aが、相続人BCのうちのBに特定遺産を相続させる旨の遺言をして死亡し、特定遺産以外の相続財産についての遺産分割協議の成立前にBがCの同意なく特定遺産を第三者に売却した場合、CはBD間の売買契約を無権代理行為に準じて取り消すことができる。 | × |
| (2)②協議分割 | |||
| 1 | R01-06-2 | 共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて遺産分割協議を成立させることができる。 | ◯ |
| 2 | H29-06-2 | (Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった。)Aの死亡後、いずれもAの子であるBとCとの間の遺産分割協議が成立しないうちにBが死亡したときは、Bに配偶者Dと子Eがいる場合であっても、Aの遺産分割についてはEが代襲相続人として分割協議を行う。 | × |
| 3 | H18-12-4 | B及びCの協議により甲土地をBが取得する旨の遺産分割協議を有効に成立させた場合、後にB及びCの合意があっても、甲土地をCが取得する旨の遺産分割協議を成立させることはできない。 | × |
| 4 | H07-11-4 | 遺産分割協議の結論は、相続人の多数決によって決する。 | × |
| (2)③家庭裁判所による分割 | |||
| 1 | H11-03-3 | 遺産の分割について共同相続人間に協議が調わないとき、各共同相続人は、その分割を、相続開始地の地方裁判所に請求することができる。 | × |
| (3)効果 | |||
| 1 | R05-01-3 | 遺産分割の効力は、相続開始の時にさかのぼって生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 | ◯ |
| 2 | R01-06-4 | 遺産の分割は、共同相続人の遺産分割協議が成立した時から効力を生ずるが、第三者の権利を害することはできない。 | × |
| 3 | H11-03-4 | 遺産分割の効力は、第三者の権利を害しない範囲で、相続開始の時にさかのぼって生ずる。 | ◯ |
| (4)債務の相続 | |||
| 1 | H23-10-3 | 共同相続人のうち、被相続人の唯一の資産を相続するものは、被相続人の債務のすべてを相続する。 | × |
| 2 | H19-12-3 | 相続人が単純承認した場合、被相続人の債務も、相続人が相続分に応じて承継する。 | ◯ |
【無料公開講座】スリー・ステップ学習法
宅建学習のプロセスを3段階に分け、着実なステップアップを目指す『スリー・ステップ学習法』。この講座の特長を実際に理解・体験していただくための「無料公開講座」です。
この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。
- [Step.1]基本習得編で宅建合格に必要な基礎知識を学ぶ。
- [Step.2]一問一答編で「一問一答式」の本試験過去問で基礎知識を確認し、○×を見分ける解法テクニックを身に付ける。
- [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。
この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。

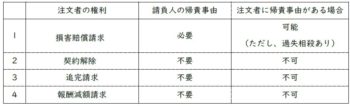

3肢につて。
「Dは、Aの死亡後で遺産分割前であっても、B及びCの同意を得なければ、自己の相続分を第三者に譲渡することはできない。」
Aが死亡したので、法定相続人がB、C、Dあり遺産はその3人が共有している状態であると思います。民法249条の規定も分かります。
疑問なのは、この遺産のことにおいて、遺言書を残さずなくなられたり、遺言書に書かれていない財産がある場合もあるのでわないかと思います。そして、遺産分割協議という相続人同士の話し合いによって、誰が遺産の次の所有者なのかを決めるのでわないかと思います。
例えば遺産を売却して現金に換えたり、被相続人が所有していた不動産を他人に貸出足りする場合には、共有状態だと共有者全員の同意を取る必要があると思います。
そういったことに於いて、この肢を○にしたいと思うのは、問題文の理解に誤りがありますでしょうか。
安東様
ご質問ありがとうございます。
宅建試験では、民法の条文、そして判例を基準にして正誤が決まります。
条文や判例と異なる学説もあるでしょうが、それは宅建試験では正解になりません。
この点で「宅建」の学習と「民法学」の学習は異なります。宅建学習上は、あくまで条文と判例、そして過去問のみを勉強するようにしましょう。
お忙しいところ、ご回答、ありがとうございました。
過去問にあたっていると、いつの間にか「民法学」的な思考になってしまっているのですね。
ちょこちょこ自覚はしているのですが、自分自身で区切りが分からない、分からないと不安で進めない性格です。
これが災いして、理解が進まなかったり、モチベーションが維持できない部分があります。
深く考えなく素直な性格なら良かったのですが。
こんなんで今年受験します。
安東様
ご返信ありがとうございました。
安東さんは、民法学の研究をなさっているんですね。
そうすると、宅建の民法は、物足りないかも知れません。
「宅建対策」としての「民法」は、条文と判例、そして過去問。この3つだけが基準です。その他の学説まで考慮すると解答不能の問題もあると思います。ご注意ください。
ありがとうございました!
どういたしまして。