
AB間で、Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲建物につき、①賃貸借契約を締結した場合と、②使用貸借契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- Bが死亡した場合、①では契約は終了しないが、②では契約が終了する。
- Bは、①では、甲建物のAの負担に属する必要費を支出したときは、Aに対しその償還を請求することができるが、②では、甲建物の通常の必要費を負担しなければならない。
- AB間の契約は、①では諾成契約であり、②でも諾成契約である。
- AはBに対して、甲建物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しなければ、①では担保責任を負う場合があるが、②では担保責任を負わない。
正解:4
1 正しい
賃借権は、被相続人の財産権の一部として、相続の対象となります。賃借人が死亡しても、賃貸借契約は終了しません。
これに対し、使用貸借は、借主の死亡によってその効力が失われます(民法599条)。つまり、使用貸借契約が終了します。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
賃貸借:相続の可否(民法[27]2(4))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
| 1 | R03-03-イ | AがA所有の建物について賃借人Bとの間で賃貸借契約を締結している期間中にAが死亡した場合、Aの相続人は、Bに賃貸借契約を継続するか否かを相当の期間を定めて催告し、期間内に返答がなければ賃貸借契約をAの死亡を理由に解除することができる。 | × |
| 2 | 27-03-1 | 借主が死亡した場合、賃貸借契約は終了しない。 | ◯ |
| 3 | 21-12-4 | 借主が死亡しても賃借権は相続される。 | ◯ |
使用貸借:相続の可否(民法[27]2(4))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
| | [共通の設定]
AB間で、Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲建物について使用貸借契約を締結した。 | |
| 1 | R03-03-エ | Bが死亡した場合、Bの相続人は、Aとの間で特段の合意をしなくても、当該使用貸借契約の借主の地位を相続して甲建物を使用することができる。 | × |
| 2 | 27-03-1 | 借主が死亡した場合、賃貸借では契約は終了しないが、使用貸借では契約が終了する。
| ◯ |
| 3 | 21-12-4 | Bが死亡すると使用貸借契約は終了するので使用借権はBの相続人に相続されない。
| ◯ |
| 4 | 17-10-1 | Bが死亡した場合、使用貸借契約は当然に終了する。
| ◯ |
| 5 | 13-06-2 | 使用貸借契約において、貸主又は借主が死亡した場合、使用貸借契約は効力を失う。
| × |
| 6 | 09-08-3 | 契約で定めた期間の満了前にBが死亡した場合には、Bの相続人は、残りの期間についても、当該建物を無償で借り受ける権利を主張することはできない。
| ◯ |
2 正しい
賃借人が必要費を支出したときは、賃貸人に対して直ちに償還を請求することができます(民法608条1項)。
一方、使用貸借においては、借主が通常の必要費を負担します(同法595条1項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
賃借人による費用の償還請求(民法[26]4(2))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
| 必要費 |
| 1 | 27-03-2 | 借主は、賃貸借契約では、貸主の負担に属する必要費を支出したときは、貸主に対しその償還を請求することができる。 | ◯ |
| 2 | 09-03-1 | 建物の賃借人が、賃借中に建物の修繕のため必要費を支出した場合、必要費の償還を受けるまで、留置権に基づき当該建物の返還を拒否できる。 | ◯ |
| 3 | 09-03-2 | 建物の賃借人の債務不履行により賃貸借契約が解除された後に、賃借人が建物の修繕のため必要費を支出した場合、必要費の償還を受けるまで、留置権に基づき建物の返還を拒否できる。 | × |
| 4 | 09-03-4 | 建物の賃借人は、留置権に基づき建物の返還を拒否している場合に、さらに当該建物の修繕のため必要費を支出したとき、その必要費のためにも留置権を行使できる。 | ◯ |
| 5 | 03-13-2 | 借主は、貸主の負担すべき必要費を支出したときは、直ちに、貸主に対しその償還を請求することができる。 | ◯ |
| 6 | 01-06-2 | 建物が老朽化してきたため、借主が貸主の負担すべき必要費を支出して建物の修繕をした場合、借主は、貸主に対して、直ちに修繕に要した費用全額の償還を請求することができる。 | ◯ |
| 有益費 |
| 1 | 03-13-3 | Aは、有益費を支出したときは、賃貸借終了の際、その価格の増加が現存する場合に限り、自らの選択によりその費した金額又は増加額の償還を請求することができる。 | × |
使用貸借(民法[27]1&2)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
| 契約の成立 |
| 1 | 27-03-3 | 貸主と借主との間の契約は、賃貸借では諾成契約であり、使用貸借でも諾成契約である。 | ◯ |
| 費用負担 |
| 1 | 27-03-2 | 借主は、使用貸借では、通常の必要費を負担しなければならない。 | ◯ |
| 2 | 09-08-4 | 借主が、借用物の通常の必要費を支出した場合には、貸主に対し、直ちに償還請求できる。 | × |
| 担保責任 |
| 1 | 27-03-4 | 貸主は借主に対して、貸借の目的物である建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しなければ、賃貸借契約では担保責任を負う場合があるが、使用貸借契約では担保責任を負わない。 | × |
3 正しい
賃貸借契約は、賃貸人と賃借人の合意のみで成立します(民法601条)。つまり、諾成契約です。契約の成立にあたって目的物の引渡しは必要ありませんし、書面により契約を締結する必要もありません。
また、使用貸借契約も、貸主と借主との合意のみで成立します(同法593条)。こちらも諾成契約です。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
賃貸借:契約の成立(民法[26]1)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
| 1 | 30-11-1 | [AとBとの間で、A所有の甲土地につき建物所有目的で賃貸借契約を締結する。]本件契約が専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする場合には、公正証書によらなければ無効となる。
| × |
| 2 | 27-03-3 | 貸主と借主との間の契約は、賃貸借では諾成契約であり、使用貸借でも諾成契約である。
| ◯ |
| 3 | 17-15-1 | 動産の賃貸借契約は、当事者の合意のみで効力を生じるが、建物の賃貸借契約は、要式契約である。 | × |
使用貸借(民法[27]1&2)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
| 契約の成立 |
| 1 | 27-03-3 | 貸主と借主との間の契約は、賃貸借では諾成契約であり、使用貸借でも諾成契約である。 | ◯ |
| 費用負担 |
| 1 | 27-03-2 | 借主は、使用貸借では、通常の必要費を負担しなければならない。 | ◯ |
| 2 | 09-08-4 | 借主が、借用物の通常の必要費を支出した場合には、貸主に対し、直ちに償還請求できる。 | × |
| 担保責任 |
| 1 | 27-03-4 | 貸主は借主に対して、貸借の目的物である建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しなければ、賃貸借契約では担保責任を負う場合があるが、使用貸借契約では担保責任を負わない。 | × |
4 誤り
賃貸借契約は、有償契約ですから、売買契約の規定が準用されます(民法559条)。したがって、目的物の契約不適合について、賃貸人は、売買契約の売主と同様の担保責任を負います(同法562~564条)。
使用貸借においては、貸主の担保責任について、贈与に関する規定が準用されています(同法596条、551条)。贈与契約についても、贈与者は、契約通りの物を引き渡すことについて担保責任を負います。ただし、贈与の目的物を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡すことを約したものという推定を受けます(同法551条)。このことにより、贈与者の担保責任が軽減されているわけです。
これを準用した使用貸借でも結論は同じです。貸主は、担保責任を負わないわけでなく、担保責任を負うもののその内容が軽減されているのです。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
使用貸借(民法[27]1&2)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
| 契約の成立 |
| 1 | 27-03-3 | 貸主と借主との間の契約は、賃貸借では諾成契約であり、使用貸借でも諾成契約である。 | ◯ |
| 費用負担 |
| 1 | 27-03-2 | 借主は、使用貸借では、通常の必要費を負担しなければならない。 | ◯ |
| 2 | 09-08-4 | 借主が、借用物の通常の必要費を支出した場合には、貸主に対し、直ちに償還請求できる。 | × |
| 担保責任 |
| 1 | 27-03-4 | 貸主は借主に対して、貸借の目的物である建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しなければ、賃貸借契約では担保責任を負う場合があるが、使用貸借契約では担保責任を負わない。 | × |
売買に関する規定の有償契約への準用(民法[24]なし)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
| 1 | 27-03-4 | 貸主は借主に対して、貸借の目的物である建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しなければ、賃貸借契約では担保責任を負う場合があるが、使用貸借契約では担保責任を負わない。
| × |
| 2 | 18-10-4 | 建物の賃借人が賃貸人の承諾なく当該建物を転貸し、無断転貸を理由に転借人が賃貸人から明渡請求を受けた場合、転借人は賃借人(転貸人)に対する賃料の全部又は一部の支払を拒むことができる。 | ◯ |
| 3 | 12-09-4 | 代物弁済として不動産の所有権の移転を受けた後は、その不動産に隠れた瑕疵があっても、弁済者の責任を追及することはできない。 | × |
| 4 | 03-13-1 | 賃貸借契約の締結に関する費用は、賃貸人と賃借人が平等な割合で負担する。 | ◯ |
>>年度目次に戻る
【無料公開講座】スリー・ステップ学習法
宅建学習のプロセスを3段階に分け、着実なステップアップを目指す
『スリー・ステップ学習法』。この講座の特長を実際に理解・体験していただくための「無料公開講座」です。
- [Step.1]基本習得編で宅建合格に必要な基礎知識を学ぶ。
- [Step.2]一問一答編で「一問一答式」の本試験過去問で基礎知識を確認し、○×を見分ける解法テクニックを身に付ける。
- [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。
この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。
![]()

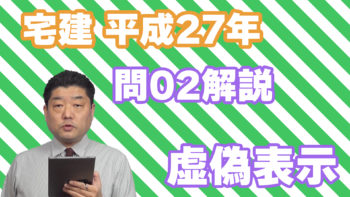
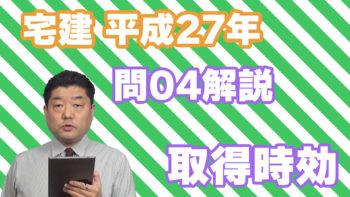
平成27年度の過去問を勉強中ですが、本文とこちらの問題の中身に相違があるようです。問3、①諾成契約②諾成契約、一方では①諾成契約②要物契約・・
他にも所々あるようです。どういうことでしょうか?
キキ様
ご質問ありがとうございます。
当サイトに掲載している過去問は、法改正を踏まえ、
「次回の本試験で出題された場合」
の問題文に修正してあります。
そうしないと、受験対策として役に立たないからです。
したがって、出題時の問題文とは変わっている点があります。
また、法改正への対応方法は、出版社や講師によって異なります。
他社さんの問題文と一致しないこともあります。