【宅建過去問】(平成28年問06)売主の責任
![]()
| 解説動画を視聴する方法 | 受講料 | |
|---|---|---|
| 1 | eラーニング講座[Step.3]過去問演習編を受講する。 | 980円/回 |
| 2 | YouTubeメンバーシップに登録する。 | 1,790円/月~ |
- Bが、甲土地がCの所有物であることを知りながら本件契約を締結した場合、Aが甲土地の所有権を取得してBに移転することができないときは、BはAに対して、損害賠償を請求することができる。
- Bが、甲土地がCの所有物であることを知りながら本件契約を締結した場合、Aが甲土地の所有権を取得してBに移転することができないときは、Bは、本件契約を解除することができる。
- Bが、A所有の甲土地が抵当権の目的となっていることを知りながら本件契約を締結した場合、当該抵当権の実行によってBが甲土地の所有権を失い損害を受けたとしても、BはAに対して、損害賠償を請求することができない。
- Bが、A所有の甲土地が抵当権の目的となっていることを知りながら本件契約を締結した場合、当該抵当権の実行によってBが甲土地の所有権を失ったときは、Bは、本件契約を解除することができる。
正解:3
1 正しい
他人物売買も契約として有効です。この契約により、売主Aは、Cから甲土地の所有権を取得して買主Bに移転する義務を負います(民法561条)。
Aが甲土地の権利をBに移転することができなければ、Bに対する債務不履行です。この場合、Bは、Aに対して損害賠償を請求することができます(同法415条)。甲土地がCの所有物であることを知っているかどうかによって、結論は、異なりません。
※他人物売買の場合、債務不履行責任を追及するために、買主は、損害賠償と契約の解除という手段を使うことができます。甲土地の所有権を一切取得することができないケースですから、追完請求や代金減額請求は、検討する必要がありません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
他人物売買:売主の債務不履行(民法[24]1(3)③)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| [共通の設定] Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約を締結した。 | |||
| 1 | 28-06-1 | Bが、甲土地がCの所有物であることを知りながら本件契約を締結した場合、Aが甲土地の所有権を取得してBに移転することができないときは、BはAに対して、損害賠償を請求することができる。 | ◯ |
| 2 | 28-06-2 | Bが、甲土地がCの所有物であることを知りながら本件契約を締結した場合、Aが甲土地の所有権を取得してBに移転することができないときは、Bは、本件契約を解除することができる。 | ◯ |
| 3 | 17-09-1 | 買主が、売主以外の第三者の所有物であることを知りつつ売買契約を締結し、売主が売却した当該目的物の所有権を取得して買主に移転することができない場合には、買主は売買契約を解除するととともに、損害賠償を請求することができる。 | ◯ |
| 4 | 16-10-2 | Aは、C所有の土地を自ら取得するとしてBに売却したが、Aの責に帰すべき事由によってCから所有権を取得できず、Bに所有権を移転できない場合、Bは、他人物売買であることを知っていたときであっても、Aに対して損害賠償を請求できる。 | ◯ |
| 5 | 08-08-1 | この土地がCの所有であることをBが知って契約した場合でも、Aがこの土地をCから取得してBに移転できないときには、Aは、Aに対して契約を解除することができる。 | ◯ |
| 6 | 05-08-3 | 甲土地のすべてがCの所有地で、AがBに移転することができなかった場合、Bは、善意悪意に関係なく、契約を解除することができる。 | ◯ |
| 7 | 03-11-2 | その土地の全部が他人のものであって、AがBに権利を移転することができないとき、買主の善意悪意に関係なく、契約を解除することができる。 | ◯ |
2 正しい
(肢1参照。)
Aに債務不履行があった場合、Bは、契約を解除することができます(民法541条、542条)。甲土地がCの所有物であることを知っているかどうかによって、結論は、異なりません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
他人物売買:売主の債務不履行(民法[24]1(3)③)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| [共通の設定] Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約を締結した。 | |||
| 1 | 28-06-1 | Bが、甲土地がCの所有物であることを知りながら本件契約を締結した場合、Aが甲土地の所有権を取得してBに移転することができないときは、BはAに対して、損害賠償を請求することができる。 | ◯ |
| 2 | 28-06-2 | Bが、甲土地がCの所有物であることを知りながら本件契約を締結した場合、Aが甲土地の所有権を取得してBに移転することができないときは、Bは、本件契約を解除することができる。 | ◯ |
| 3 | 17-09-1 | 買主が、売主以外の第三者の所有物であることを知りつつ売買契約を締結し、売主が売却した当該目的物の所有権を取得して買主に移転することができない場合には、買主は売買契約を解除するととともに、損害賠償を請求することができる。 | ◯ |
| 4 | 16-10-2 | Aは、C所有の土地を自ら取得するとしてBに売却したが、Aの責に帰すべき事由によってCから所有権を取得できず、Bに所有権を移転できない場合、Bは、他人物売買であることを知っていたときであっても、Aに対して損害賠償を請求できる。 | ◯ |
| 5 | 08-08-1 | この土地がCの所有であることをBが知って契約した場合でも、Aがこの土地をCから取得してBに移転できないときには、Aは、Aに対して契約を解除することができる。 | ◯ |
| 6 | 05-08-3 | 甲土地のすべてがCの所有地で、AがBに移転することができなかった場合、Bは、善意悪意に関係なく、契約を解除することができる。 | ◯ |
| 7 | 03-11-2 | その土地の全部が他人のものであって、AがBに権利を移転することができないとき、買主の善意悪意に関係なく、契約を解除することができる。 | ◯ |
3 誤り
抵当権が設定された不動産を購入し、その抵当権が実行されたことにより、買主が不動産の所有権を失いました。これにより、AがBに対して甲土地の所有権を移転する義務が債務不履行(履行不能)になったわけです。
この場合、Bは、Aに対して、損害賠償を請求することができます(肢1参照)。買主の善意・悪意は、問われません。
本肢は、「知りながら本件契約を締結した場合……損害賠償を請求することができない」とする点が誤りです。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
売主の担保責任(抵当権・地上権等がある場合)(民法[24]3(3)③)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 抵当権がある場合 | |||
| [共通の設定] Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約を締結した。甲土地には、Cを抵当権者とする抵当権が設定され、その登記もされていた。 | |||
| 1 | 28-06-3 | Bが、A所有の甲土地が抵当権の目的となっていることを知りながら本件契約を締結した場合、当該抵当権の実行によってBが甲土地の所有権を失い損害を受けたとしても、BはAに対して、損害賠償を請求することができない。 | × |
| 2 | 28-06-4 | Bが、A所有の甲土地が抵当権の目的となっていることを知りながら本件契約を締結した場合、当該抵当権の実行によってBが甲土地の所有権を失ったときは、Bは、本件契約を解除することができる。 | ◯ |
| 3 | 20-09-2 | 甲土地に設定されている抵当権が実行されてBが所有権を失った場合、Bが甲土地に抵当権が設定されていることを知っていたとしても、BはAB間の売買契約を解除することができる。 | ◯ |
| 4 | 17-09-3 | 買主が、抵当権が存在していることを知りつつ不動産の売買契約を締結し、当該抵当権の行使によって買主が所有権を失った場合には、買主は、売買契約の解除はできるが、売主に対して損害賠償請求はできない。 | × |
| 5 | 11-10-3 | AがCに設定していた契約の内容に適合しない抵当権の実行を免れるため、BがCに対しAの抵当債務を弁済した場合で、BがAB間の契約締結時に抵当権の存在を知っていたとき、Bは、Aに対し、損害の賠償請求はできないが、弁済額の償還請求はすることができる。 | × |
| 6 | 08-08-3 | この土地が抵当権の目的とされており、その実行の結果Dが競落したとき、Bは、Aに対して契約を解除することができる。 | ◯ |
| 7 | 04-06-3 | Bは、Cの抵当権が設定されていることを知らなかったときであっても、Cが抵当権を実行する前においては、Aに対し、売買契約を解除することができない。 | × |
| 8 | 02-06-1 | Aは、契約の際Cの抵当権のあることを知らなくても、その理由だけでは、AB間の売買契約を解除することはできない。 | ◯ |
| 9 | 01-04-4 | その土地に抵当権が設定されていて、買主がそのことを知らなかったときであっても、買主は、その事実を知ったとき、抵当権が行使された後でなければ、契約を解除することができない。 | × |
| 地上権がある場合 | |||
| 1 | 05-08-4 | 売買の目的物である土地に第三者が登記済みの地上権を有していて、買主が利用目的を達成することができなかった場合、善意悪意に関係なく、契約を解除することができる。 | ◯ |
4 正しい
(肢1・3参照。)
Aに債務不履行があった場合、Bは、契約を解除することができます(民法542条)。買主の善意・悪意は、問われません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
売主の担保責任(抵当権・地上権等がある場合)(民法[24]3(3)③)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 抵当権がある場合 | |||
| [共通の設定] Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約を締結した。甲土地には、Cを抵当権者とする抵当権が設定され、その登記もされていた。 | |||
| 1 | 28-06-3 | Bが、A所有の甲土地が抵当権の目的となっていることを知りながら本件契約を締結した場合、当該抵当権の実行によってBが甲土地の所有権を失い損害を受けたとしても、BはAに対して、損害賠償を請求することができない。 | × |
| 2 | 28-06-4 | Bが、A所有の甲土地が抵当権の目的となっていることを知りながら本件契約を締結した場合、当該抵当権の実行によってBが甲土地の所有権を失ったときは、Bは、本件契約を解除することができる。 | ◯ |
| 3 | 20-09-2 | 甲土地に設定されている抵当権が実行されてBが所有権を失った場合、Bが甲土地に抵当権が設定されていることを知っていたとしても、BはAB間の売買契約を解除することができる。 | ◯ |
| 4 | 17-09-3 | 買主が、抵当権が存在していることを知りつつ不動産の売買契約を締結し、当該抵当権の行使によって買主が所有権を失った場合には、買主は、売買契約の解除はできるが、売主に対して損害賠償請求はできない。 | × |
| 5 | 11-10-3 | AがCに設定していた契約の内容に適合しない抵当権の実行を免れるため、BがCに対しAの抵当債務を弁済した場合で、BがAB間の契約締結時に抵当権の存在を知っていたとき、Bは、Aに対し、損害の賠償請求はできないが、弁済額の償還請求はすることができる。 | × |
| 6 | 08-08-3 | この土地が抵当権の目的とされており、その実行の結果Dが競落したとき、Bは、Aに対して契約を解除することができる。 | ◯ |
| 7 | 04-06-3 | Bは、Cの抵当権が設定されていることを知らなかったときであっても、Cが抵当権を実行する前においては、Aに対し、売買契約を解除することができない。 | × |
| 8 | 02-06-1 | Aは、契約の際Cの抵当権のあることを知らなくても、その理由だけでは、AB間の売買契約を解除することはできない。 | ◯ |
| 9 | 01-04-4 | その土地に抵当権が設定されていて、買主がそのことを知らなかったときであっても、買主は、その事実を知ったとき、抵当権が行使された後でなければ、契約を解除することができない。 | × |
| 地上権がある場合 | |||
| 1 | 05-08-4 | 売買の目的物である土地に第三者が登記済みの地上権を有していて、買主が利用目的を達成することができなかった場合、善意悪意に関係なく、契約を解除することができる。 | ◯ |
【無料公開講座】スリー・ステップ学習法
宅建学習のプロセスを3段階に分け、着実なステップアップを目指す『スリー・ステップ学習法』。この講座の特長を実際に理解・体験していただくための「無料公開講座」です。
この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。
- [Step.1]基本習得編で宅建合格に必要な基礎知識を学ぶ。
- [Step.2]一問一答編で「一問一答式」の本試験過去問で基礎知識を確認し、○×を見分ける解法テクニックを身に付ける。
- [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。
この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。

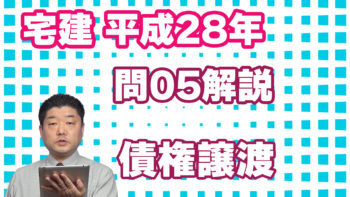
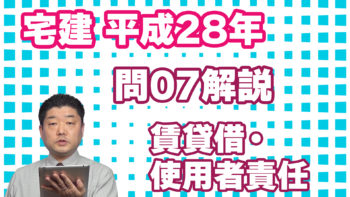
肢1の解説の最後の行に、「追完請求や代金減額請求は、検討する必要がありません。」と明記されていますが、これは、目的物の「全部」が他人の物である場合ですか?
もしも、目的物の「一部が」他人の物である場合で、売主に債務不履行があった場合は、損害賠償請求、契約の解除、追完請求、代金減額請求は出来ますか?
はやと様
ご質問ありがとうございます。
契約不適合担保責任の性質
そもそも、契約不適合担保責任というのは、「買主に引き渡された目的物や買主に移転した権利が、種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しないときに、売主が買主に対して負う債務不履行責任」です。
つまり、「引渡しがあった」場合にしか発生しません。
(債務不履行の3類型でいえば「不完全履行」のケースです。)
債務不履行については、[Step.1]基本習得編で、以下の箇所を見直しておきましょう。
■民法[15]債務不履行
2.債務不履行の要件
この問題では
選択肢1と2では、「甲土地がCの所有物である」ため「Aが甲土地の所有権を取得してBに移転することができない」という状況です。権利が引き渡されていないのですから、契約不適合担保責任の問題は発生しません。
通常の債務不履行(そのうち履行不能)の問題として処理することになります。
一部他人物売買の場合
「土地の『一部が』他人の物」であっても、その部分を売主が他人から買い取って買主に引き渡すことができれば、通常は問題ありません。
契約不適合担保責任が発生するのは、「引渡しはした」けれども、その物が「契約の内容に適合しないものだった」というケースです。例えば、「他人所有の土地を買い取ることができず、契約した土地の『全部』を引き渡すことができなかった。」というのであれば、契約不適合担保責任が生じます。
この点については、[Step.1]の以下のところを復習してください。
■民法[24]売買契約
3.売主の契約不適合担保責任
足の1番、3番について、教えてください。
損害賠償とあわせて契約解除も、同時に請求できますか?
もちろん可能です。
契約の解除は、「契約関係を当初にさかのぼってなかったことにする」という意味しか持ちません。
買主に損害が発生している場合には、契約を解除するだけでなく、これに加えて、損害の賠償を求めることができます。
これは、過去に5回も出題されている重要論点です。
この機会に、基本講義に戻って、しっかり確認しておきましょう。
参照箇所は、以下のところです。
■民法[23]契約の解除
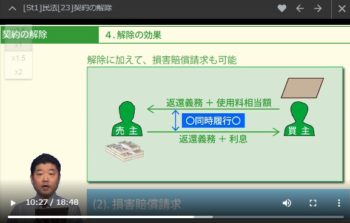
4.解除の効果
(2).損害賠償請求
回答ありがとうございました。基本に戻って再確認します。
基本が何より重要です。
悩んだときは、[Step.1]基本習得編に戻って、講義内容を確認してください。
こんにちは。私の理解不足で質問が重複していたらすみません。
「Bが甲土地の所有権を失ったとき」とあるので、所有権を手に入れるという目的が一度果たされたあとで抵当権の実行により所有権を失ったという状況だと思ったのですが、それでも目的物が引き渡されていない=契約不適合として損害賠償が可能ということですか?
marme様
ご質問ありがとうございます。
売主Aの義務は、「とりあえず一時的にでもBに所有権を移転させればOK」というものではありません。
一時的にBの所有物になったとしても、その後、「抵当権の実行によってBが甲土地の所有権を失」っているのです。
結局、Aが設定した抵当権の実行が原因で、Bは、所有権を失っています。この場合、Aが「Bに権利を移転することができなかった」と評価されます。つまり、Aの債務不履行(履行不能)です。
Bは、Aに対して損害賠償を請求し(肢3)、売買契約を解除することができます(肢4)。
分かりやすい解説をいつも参考にさせていただいております。
選択肢(3)(4)の抵当権付き不動産売買について質問ですが、
元々抵当権などの担保権付きの不動産を、その事を「知っていて(悪意で)」購入する様な場合は、そもそも抵当権が実行されて所有権を失うリスクを「承知の上」で安く購入しているケースが多いと思うのですが、それにもかかわらず、抵当権が実行されて所有権を失った時には、解除や損害賠償が可能という事なるのでしょうか?
また、この様な担保権付き不動産の売買の場合、責任追及の期間の制限につきましては、どの様な基準となるのでしょうか?
(種類又は品質以外の権利の不適合という事で、単純に566条の「知ってから1年、引渡しから10年」の適用外となるのか?)
お忙しい中恐れ入りますが、ご教示願います。
ホギ様
ご質問ありがとうございます。
回答が遅くなり、大変申し訳ありません。
買主が抵当権の存在を知っていても知らなくても、買主がその不動産の所有権を手に入れることができなかった、という事実は、変わりません。
つまり、売主は、
「目的物を引き渡す」
という義務を履行できなかったわけです。
これは債務不履行(履行不能)ですから、買主は、契約を解除し、損害賠償を請求することができます。
566条の期間制限(不適合を知った時から1年以内に通知)が適用されるのは、「目的物の種類又は品質」に関する不適合に限られます。
この制限は、「権利」に関する契約不適合には、適用されません。したがって、一般的な消滅時効のみを考えることになります。