【宅建過去問】(平成23年問44)監督処分
| 解説動画を視聴する方法 | 受講料 | |
|---|---|---|
| 1 | eラーニング講座[Step.3]過去問演習編を受講する。 | 980円/回 |
| 2 | YouTubeメンバーシップに登録する。 | 1,790円/月~ |
- 国土交通大臣は、すべての宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対し、業務の停止を命じ、又は必要な指示をしようとするときは聴聞を行わなければならない。
- 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法に違反した場合に限り、監督処分の対象となる。
- 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第31条の3に規定する専任の宅地建物取引士の設置要件を欠くこととなった場合、2週間以内に当該要件を満たす措置を執らなければ監督処分の対象となる。
正解:3
1 正しい
国土交通大臣はすべての宅建業者に対して、知事は都道府県の区域内で宅建業を営む宅建業者に対して、必要な指導、助言及び勧告をすることができます(宅建業法71条)。
※指導・助言・勧告などは行政指導であり、指示・業務停止・免許取消しなどの処分(行政行為)とは大きく異なります。行政指導を行うにあたり、事前の聴聞は不要ですし、行政指導の事実が公告されることもありません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
指導・助言・勧告(宅建業法[22]2(7))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | H30-32-3 | 国土交通大臣は、すべての宅地建物取引士に対して、購入者等の利益の保護を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。 | × |
| 2 | H27-43-4 | 宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)は、甲県内に所在する事務所について、業務に関する帳簿を備えていないことが判明した。この場合、Aは、甲県知事から必要な報告を求められ、かつ、指導を受けることがある。 | ◯ |
| 3 | H23-44-1 | 国土交通大臣は、すべての宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。 | ◯ |
| 4 | H22-44-1 | 国土交通大臣は、宅地建物取引業者(甲県知事免許)に対し、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要な勧告をしたときは、遅滞なく、その旨を甲県知事に通知しなければならない。 | × |
| 5 | H21-45-3 | 国土交通大臣は、宅地建物取引業者(甲県知事免許)に対し宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。 | ◯ |
| 6 | H12-43-2 | 国土交通大臣は、宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対し宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることはあっても、Aの免許を取り消すことはできない。 | ◯ |
2 正しい
宅建業者に対する指示処分に限らず、宅建業法上の監督処分をするときには、聴聞を行う必要があります(宅建業法69条1項)。
「弁明の機会の付与」(聴聞より簡易な手続)で済ませることはできません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
監督処分(聴聞手続)(宅建業法[22]2(4)①)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R01-29-イ | 甲県知事は、宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 | ◯ |
| 2 | H24-44-1 | 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対して必要な指示をしようとするときは、行政手続法に規定する弁明の機会を付与しなければならない。 | × |
| 3 | H23-44-2 | 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対し、業務の停止を命じ、又は必要な指示をしようとするときは聴聞を行わなければならない。 | ◯ |
| 4 | H21-45-2 | 甲県知事は、宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、その期日における審理は、公開により行わなければならない。 | ◯ |
| 5 | H14-39-3 | 都道府県知事は、宅地建物取引業者に対し、業務停止処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならないが、指示処分をするときは、聴聞を行う必要はない。 | × |
| 6 | H10-32-3 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、その業務に関して広告をし、宅地建物取引業法第32条(誇大広告等の禁止)の規定に違反した場合、甲県知事は、Aに対し、行政手続法の規定による意見陳述のための手続の区分に従い、弁明の機会を付与して、業務の停止を命ずることができる。 | × |
| 7 | H05-49-4 | 甲県知事が宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の免許を取り消す場合、Aの出頭を求めて公開による聴聞を行わなければならないが、A又はAの代理人が正当な理由なく聴聞の期日に出頭しないときは、甲県知事は、聴聞を行わないで、取り消すことができる。 | ◯ |
3 誤り
宅建業法に違反していない場合でも、業務に関し法令に違反し、宅建業者として不適当であると認められるときは、監督処分(指示、業務停止、免許取消し)の対象となります(宅建業法65条1項3号、2項1号の2、66条1項9号)。
例えば、宅建業の業務に関して、建築基準法や国土利用計画法に違反した場合も、監督処分を受けることがあります。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
宅建業法以外の違反に対する監督処分(宅建業法[22]2(1)②・(2)②)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | H29-29-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、マンション管理業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとして、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、国土交通大臣から業務の停止を命じられた。この場合、Aは、甲県知事から法に基づく指示処分を受けることがある。 | × |
| 2 | H23-44-3 | 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法に違反した場合に限り、監督処分の対象となる。 | × |
| 3 | H18-45-4 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の取締役が宅地建物取引業の業務に関し、建築基準法の規定に違反したとして罰金刑に処せられた場合、甲県知事は、Aに対して必要な指示をすることができる。 | ◯ |
| 4 | H14-39-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、宅地建物取引業の業務に関して、建築基準法の規定に違反して罰金に処せられた場合、これをもって業務停止処分を受けることはない。 | × |
| 5 | H14-39-4 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の取締役が宅地建物取引業の業務に関するものではないが、脱税し、所得税法に違反したとして罰金刑に処せられた場合、Aは指示処分を受けることがある。 | × |
| 6 | H04-49-1 | 宅地建物取引業者は、国土利用計画法の規定に違反して刑罰に処せられた場合、これに伴い、宅地建物取引業法の罰則の適用を受けることはないが、業務停止処分を受けることはある。 | ◯ |
| 7 | H02-44-イ | 宅地建物取引業者A社の取締役Bが、Bの所有地の売却に伴う譲渡所得について脱税し、所得税法に違反したとして、罰金の刑に処せられた場合、A社は、宅地建物取引業法に基づく監督処分の対象となることがある。 | × |
| 8 | H02-44-ウ | 宅地建物取引業者Aが、分譲マンションの建築確認を受けず、かつ、再三特定行政庁の工事施工停止命令に従わず、建築基準法に違反したとして、罰金の刑に処せられた場合、Aは、宅地建物取引業法に基づく監督処分の対象となることがある。 | ◯ |
| 9 | H02-44-エ | 宅地建物取引業者Aが、団地造成の許認可の便宜を図ってもらうため、賄賂を供与し、刑法第198条の罪(贈賄罪)を犯したとして、罰金の刑に処せられた場合、Aは、宅地建物取引業法に基づく監督処分の対象となることがある。 | ◯ |
4 正しい
専任宅建士が法定数に不足した場合、宅建業者は2週間以内に必要な措置を執る必要があります(宅建業法31条の3第3項)。これに違反した場合、指示処分や業務停止処分という監督処分の対象となります(同法65条1項、2項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
専任宅建士の人数が不足した場合(宅建業法[08]1(5))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R04-26-4 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、30日以内に必要な措置を執らなければならない。 | × |
| 2 | R03s-41-2 | 宅地建物取引業者は、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士が退職したときは、2週間以内に、宅地建物取引業法第31条の3第1項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。 | ◯ |
| 3 | R02s-38-ア | 宅地建物取引業者は、事務所に置く唯一の専任の宅地建物取引士が退任した場合、その日から30日以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置し、その設置の日から2週間以内に、専任の宅地建物取引士の変更があった旨を免許権者に届け出なければならない。 | × |
| 4 | R01-35-2 | 宅地建物取引業者は、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士Aが令和X年5月15日に退職したため、同年6月10日に新たな専任の宅地建物取引士Bを置いた。 | × |
| 5 | H24-36-1 | 宅地建物取引業者A社は、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士が退職したときは、30日以内に、新たな専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。 | × |
| 6 | H23-44-4 | 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第31条の3に規定する専任の宅地建物取引士の設置要件を欠くこととなった場合、2週間以内に当該要件を満たす措置を執らなければ監督処分の対象となる。 | ◯ |
| 7 | H22-29-4 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、2週間以内に必要な措置を執らなければならない。 | ◯ |
| 8 | H19-30-3 | 宅地建物取引業者Aは、その事務所の専任の宅地建物取引士Bが3か月間入院したため、宅地建物取引業法第31条の3に規定する専任の宅地建物取引士の設置要件を欠くこととなったが、その間、同条の規定に適合させるために必要な措置を執らなかった。この場合、Bは指示処分の対象になるが、業務停止処分の対象にはならない。 | × |
| 9 | H18-31-1 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の唯一の専任の宅地建物取引士であるBが退職したとき、A社は2週間以内に新たな成年者である専任の宅地建物取引士を設置し、設置後30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
| 10 | H18-36-1 | 宅地建物取引業者は、既存の事務所に置かれている成年者である専任の宅地建物取引士の数が国土交通省令に規定する数を下回ったときは、直ちに、当該事務所を閉鎖しなければならない。 | × |
| 11 | H14-36-3 | 宅地建物取引業者は、その「事務所」だけでなく国土交通省令で定める場所ごとに一定の専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、これに抵触することとなった場合は、2週間以内に必要な措置を執らなければならない。 | ◯ |
| 12 | H07-50-1 | 甲県に本店(従業者13人)、乙県に支店(従業者5人)を有する個人である宅地建物取引業者Aは、本店の専任の宅地建物取引士が2人となったときは直ちに宅地建物取引業法違反となり、甲県知事は、Aに対して業務停止処分をすることができる。 | × |
| 13 | H04-49-2 | 宅地建物取引業者は、事務所に置かなければならない専任の宅地建物取引士が退職して欠員を生じた場合、2週間以内に是正措置を講じないと、業務停止処分を受けることはあるが、罰則の適用を受けることはない。 | × |
【無料公開講座】スリー・ステップ学習法
宅建学習のプロセスを3段階に分け、着実なステップアップを目指す『スリー・ステップ学習法』。この講座の特長を実際に理解・体験していただくための「無料公開講座」です。
この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。
- [Step.1]基本習得編で宅建合格に必要な基礎知識を学ぶ。
- [Step.2]一問一答編で「一問一答式」の本試験過去問で基礎知識を確認し、○×を見分ける解法テクニックを身に付ける。
- [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。
この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。

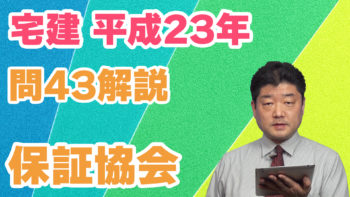

肢2についてですが、禁錮以上の刑に処せられて免許を取り消される場合も聴聞が必要だということでしょうか。
「禁錮以上の刑に処せられ」たケースでは、免許取消事由に該当することを、裁判所の判決書で証明することができます。
このようなケースでは、聴聞手続きを行う必要がありません。
しかし、これはあくまで「行政手続法」の問題です(同法13条2項2号)。宅建試験の「宅建業法」で出題されたことはありませんし、今後の出題も考えられません。
宅建試験の出題は、いつも同じパターンです。
(肢2の「■類似過去問」を見てみてください。)
これらのヒッカケ・パターンに対応できれば、宅建試験対策は十分です。
ありがとうございます。
助かりました。
どういたしまして。