【宅建過去問】(平成24年問03)民法に規定されているもの
![]()
| 解説動画を視聴する方法 | 受講料 | |
|---|---|---|
| 1 | eラーニング講座[Step.3]過去問演習編を受講する。 | 980円/回 |
| 2 | YouTubeメンバーシップに登録する。 | 1,790円/月~ |
【注意】
「民法の条文に規定されているかどうか」を問う問題は、民法改正を控えた平成24年~29年の6年間に渡り出題されました。令和2年に改正民法が施行されたため、今後この形式で出題される可能性は低いです。ここでは、改正後の民法に合うように問題を修正して掲載しています。
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはいくつあるか。
- ア 意思能力を欠く状態でなされた意思表示が無効である旨
- イ 契約締結に当たって当事者が基礎とした事情に変更が生じた場合に、当事者は契約の再交渉を求めることができる旨
- ウ 保証契約は、書面でしなければその効力を生じない旨
- エ 物の瑕疵とは、目的物が備えるべき性質、品質を備えていないことである旨
- なし
- 一つ
- 二つ
- 三つ
正解:3
ア 条文に規定されている
意思能力とは、自己の行為の結果を判断することができる精神的能力のことをいいます。例えば、精神上の障害や泥酔により、意思能力を欠く状態で意思表示を行った場合、その意思表示は、当初から無効と扱うわけです(民法3条の2)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
意思能力(民法[01]1(2))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R03-05-4 | 意思能力を有しないときに行った不動産の売買契約は、後見開始の審判を受けているか否かにかかわらず効力を有しない。 | ◯ |
| 2 | H30-03-4 | AとBとの間で、A所有の甲建物をBに贈与する旨を書面で約した。本件約定の時点でAに意思能力がなかった場合、Bは、本件約定に基づき甲建物の所有権を取得することはできない。 | ◯ |
| 3 | H24-03-1 | 意思能力を欠く状態での意思表示は、無効である。 | ◯ |
| 4 | H20-01-1 | 成年被後見人が行った法律行為は、事理を弁識する能力がある状態で行われたものであっても、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りではない。 | ◯ |
| 5 | H19-01-4 | A所有の甲土地についてのAB間の売買契約が、Aが泥酔して意思無能力である間になされたものである場合、Aは、酔いから覚めて売買契約を追認するまではいつでも売買契約を取り消すことができ、追認を拒絶すれば、その時点から売買契約は効となる。 | × |
| 6 | H17-01-2 | 自己所有の土地を売却するAの売買契約の相手方である買主Bが意思無能力者であった場合、Bは、Aとの間で締結した売買契約を取り消せば、当該契約を無効にできる。 | × |
| 7 | H15-01-1 | 意思能力を欠いている者が土地を売却する意思表示を行った場合、その親族が当該意思表示を取り消せば、取消しの時点から将来に向かって無効となる。 | × |
| 8 | H02-04-1 | A所有の土地が、AからBへと売り渡された。Aが成年被後見人の場合、Aは、契約の際完全な意思能力を有していてもAB間の契約を取り消し、Cに対して所有権を主張することができる。 | ◯ |
イ 条文に規定されていない
本肢の考え方を事情変更の原則といいます。このことにつき、民法に明文の規定はありません。信義誠実の原則(同法1条2項)を根拠に、判例により導かれた原則です。
ウ 条文に規定されている
保証契約については、「保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。」と定められています(民法446条2項。電磁的記録でも書面による契約とみなされます)。これを「保証契約の要式性」といいます。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
保証契約の成立(民法[18]1(2))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 契約当事者 | |||
| 1 | H22-08-1 | 保証人となるべき者が、主たる債務者と連絡を取らず、同人からの委託を受けないまま債権者に対して保証したとしても、その保証契約は有効に成立する。 | ◯ |
| 要式契約 | |||
| 1 | R02-02-1 | ケース①(個人Aが金融機関Bから事業資金として1,000万円を借り入れ、CがBとの間で当該債務に係る保証契約を締結した場合)の保証契約は、口頭による合意でも有効であるが、ケース②(個人Aが建物所有者Dと居住目的の建物賃貸借契約を締結し、EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務に係る保証契約を締結した場合)の保証契約は、書面でしなければ効力を生じない。 | × |
| 2 | H27-01-2 | 事業のために負担した貸金債務を主たる債務とする保証契約は、保証人になろうとする個人が、契約締結の日の前1か月以内に作成された公正証書で保証債務を履行する意思を表示していなければ無効となる。 | ◯ |
| 3 | H24-03-3 | 保証契約は、書面でしなければその効力を生じない。 | ◯ |
| 4 | H22-08-2 | 口頭での意思表示で保証契約が成立する。 | × |
| 保証人の責任 | |||
| 1 | H25-07 | 判決文の読み取り問題 | |
エ 条文に規定されていない
令和2年施行の改正民法では、それまでの「瑕疵担保責任」というアプローチではなく、「契約不適合担保責任」という考えかたを採用しています(同法562条、563条など)。このため「瑕疵」に関する定義は不要であり、民法上の規定も存在しません。

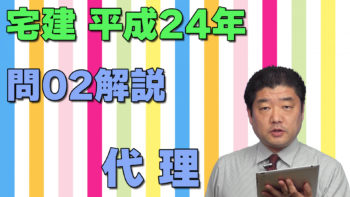
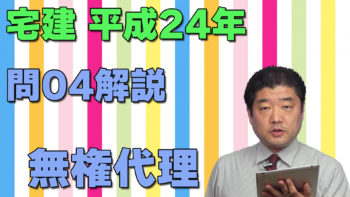
よく見たら、問題文と解説の順序が逆ですが掲載されていました。
失礼しました。
了解しました。
問題文が掲載されていません。